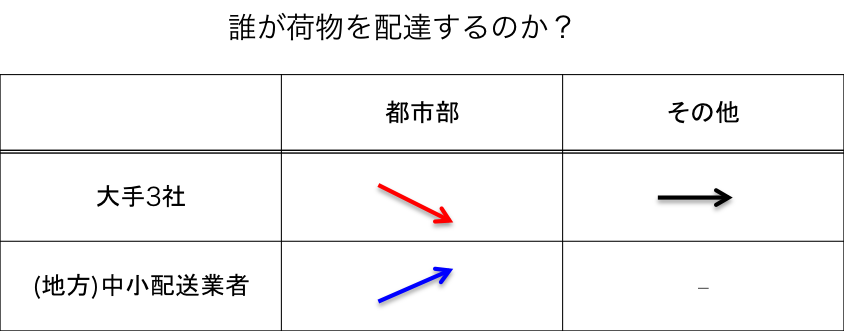WMSとは?
Warehouse Management Systemの略で、日本語でいうと、倉庫管理システムのことである。倉庫に入荷された物が出荷されるまでの工程を管理するもので、入荷管理、在庫管理、出荷管理、各種帳票作成などの機能がある。
導入するにあたって、まず導入目的を明確にする。成し遂げたい業務やそのKPI(物が倉庫に着荷後24時間以内に出荷等)の達成である。費用対効果、スケジュール、社内外を問わず必要な人的リソースの確保も含めて優先順位をつけて、何を(what)、どこまで(how far)、どうやって(how)、いつまでに(by when)実施するのかを事前に社内でマネージメント層含めて合意することが大切である。
優先順位をつけないと、”何を(what)”が話し合いを重ねてゆく中で、ドンドン膨れ上がり、予算やスケジュールに影響を与えることになりかねない。倉庫の立ち上げの日が発表され、要件定義や基本設計を重ねている中で要件が膨らみ、開発やテストの工数が削減され、倉庫を立ち上げたは良いもののエラーが頻発し、そのリカバリー処理で現場が疲弊することが起きる。
WMS導入の主要パターン
WMSを新規に導入するには下記の3パターンがあると考える。
①スクラッチで開発して利用
②パッケージをカスタマイズして利用
③パッケージを利用
WMSを利用する目的のビジネス要件を満たすためにどれが最適かを見極める必要がある。費用、期間、人的工数、検証工数の観点も踏まえて簡単に下記にまとめる。
工数がかからないのは、楽天、アマゾン、Shopifyのeコマースサイトから受注管理ソフトで注文情報を集約してWMSに流し込むという、上記’③パッケージをそのまま利用する’というパターンで、早ければ1ヶ月程度で完了します。ビジネス上の要件が複雑でなく、パターン化されているために実現可能なパターンです。
逆に工数がかかるのは、日に数十万件も出荷するような’①スクラッチで開発を実施する’もので、要件定義から立ち上げまで1-2年かかることもあります。
いずれのパターンにせよ、マネジメント層含めてWMS導入のGOALを設定することが大切になる。